 |
 |
|
|
チャーン帝国、辺境の酒場にて、夕刻。 このころ、人は椅子に腰を落ち着け、ただ腹へモノをおさめる。 だれしもに共通する憩いの時間。そうであるからこそ、騒がしい世間を忘れて安らかに過ごせる貴重なあわい。 だのに。 おれのまわりにいる厳つい男どもはみな総立ちになり、めいめいが手持ちの得物を構えて肩を怒らせ、「しゃあ」だの「おらあ」だの、獰猛な鳴き声を発して、おれの噛むメシの味をひたすらに不味くさせる。 ふって湧いた暴力の気配に、力はもたずとも賢い村民は食いさしの皿もそのままにそそくさと酒場から逃げ出し、何もない酔いどれは恐れと好奇心で満たした眼を押し広げてちびちび酒をあおった。 おれはというと、いつになったら店が気を利かせておかわりを勧めてくるか、心待ちにしながら手元の器を弄っていた。 言い訳をさせてもらうのなら、そのときのおれは疲れていて、かつ腹が減っていた。 注意が散漫になっていたとしてもしかたがない。 けれど、きっとくたばる寸前まで後悔することになる。 ああしまった。 あのときにさっさと別の店を探しとくんだった。 だって、店員みんなサッサとずらかって、隣の店でヤケ酒あおってたんだから。 そうしていたなら、きっと、おれはあの魔女を目にすることさえなかったのに。 「あんたって勇者だろ」 ごろつきどものみっともないケンカを眺めるのにも飽きて、喧騒に背を向けカウンターと向き合ったときだった。 店員なるものがこの店に存在しないことにうすうす気付き始めていたおれは、それでも立ち上がることさえ億劫で、結果避けられたはずの面倒ごとに真正面からぶつかった。 きっと、おれは生来のバカなんだろう。学を身に着けたところでどうしようもないたぐいの。 内心で己をののしりながら、しかたなしにその男――亀のように首を引っ込め、飛び交う凶器にビビってる酔いどれ――の相手をする。 ちょっとくたびれ過ぎて、自前の意思だけでは何もできそうになかった、というのもある。 「自分で勇者だの名乗るやつって、よっぽどの恥知らずだと思うんだ」 「はは、ちげぇねぇ」酒臭い息を木板に振りまいて、頭を低くしたまま酔いどれたオヤジはおれに賛同する。 「だがな、フシュ、あんたはそうじゃない。 あんたは正真正銘の戦士で、誰もがみとめる勇者だ。 だからさ、ホラ」 酔いどれは、チラッと後ろに視線を送る。「嫌だね」おれは温くなった器を、やっとテーブルに戻す。 「疲れてるんだよ。本当に、今日は勘弁して欲しいんだ。殺すより殺されるほうを選びたくなるくらいに。 あんたの声は煩いし、くどいし、お世辞なんて聞いてるだけで胸が焼ける」 おれが言い終えるか、終えないかというときに、ひい、と酔いどれが声を漏らす。 奴の目の前のカウンターに突き立った手斧が、びいん、と低い音を立てて震える。 「やりすぎだな、人死にが出るぞ。 おれなんぞに頼むより、さっさと若い衆に連絡すべきだと思うがね」 「違うんだ、俺があんたに頼みたいのはそんな単純なことじゃあなくってさ……」 すべてを言い終える前に、酔いどれが不意に「痛て」となんでもないことのようにつぶやき、いっそ滑稽なほど大げさに椅子から転げ落ちた。 いてえ、いいいてええええ。 あまりに唐突でおかしみを覚え、脛でも打ったのかマヌケだな、とでも、笑ってやろうと思った。 唇の端を吊り上げて、バカ笑いの準備すらして視線を下げ、そこに血の海を見た。 酔いどれの背中、ちょうど胃の真後ろに突き立ったナイフは綺麗に肝臓を貫き、溢れ出た血はどす黒い色を床に広げた。 酔いどれは、転げまわろうとしては背中のナイフに邪魔され、バタバタと脚を空回し、ぴちゃぴちゃ音を立て血を撥ね上げた。 その向こうには血まみれの男が、足元にまで達した赤色をまたいで棒立ちになり、錆びた臭気が届いたのか鼻をひくつかせ、ピクリと顔を上げて、おれの視線に気がついた。 「来れば殺す」 俺はある種の自動化された反応として、その意識もなく腰に差した曲刀【シミター】を抜き、男に切っ先を向ける。 「ひひ」男は笑い、動かなくなった酔いどれに躓きつつ、カウンターに突き立った手斧に手を伸ばそうと、おれの方へ迷いなく迫ってくる。 男の焦点の合わない目と、白目の部分に浮き上がった血管に気付いたときには既に、おれは判断し、その首を掻き切っていた。 こぼれたものによって、床へ新たに上書きされる、先ほどより鮮やかな赤色。 殺しの緊張が抜け、周囲に注意が向く。店の中は、最早ケンカによるものとは言いがたい、ひどい有様となっていた。獣のような殺し合いの跡。死体をなおも刺突する奴。最早刃もなくなった剣で、ピクリとも動かない誰かの背中をひたすらに殴打する奴。耳に障るわめき声。 狂った情景を目の端に入れたまま、首を押さえて崩れ落ちた男を蹴ってどかし、倒れた酔いどれの服を引っ張り、カウンターの裏までつれてゆく。 「災難だったな。あー、なんか言い残しとくこと、ある……」 オヤジの唇は紫色になり、脂ぎっていた顔には最早水気もない。血を失いすぎている。 長くないだろうと知り、祈り方も知らない俺が出来ることといえば、少しでもその気を紛らせることくらい。 「……魔女が、村を、おかしく……魔女を、ぁあ、糞。クソ、たれ」 おれは片膝をついて、意味を成さない言葉の羅列を聞いてやる。 悪態と、村を案じる言葉と、魔女という単語を幾度も織り交ぜたうわごとがかすれて聞こえなくなり、胸の動きが止まるまで、おれはそばについて居てやった。 |
||
この小説は 面白い(NNRに投票)/ 面白くない *これは主にネット小説ランキングから来た人に向けた評価/投票ボタンです。面白くない、についてはWEB拍手の機能を利用して集計しています。
|
||
 |
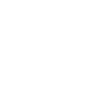 |

|
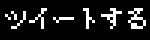
|
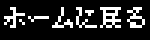 |