 |
 |
|
|
おずおずと差し出された茶碗を受け取り、一緒に渡された箸で底に沈む銀貨を拾い上げる。 魔女が客人をもてなす時は、毒を入れる意図がない、ひいては殺意がないことを示すために銀の食器を用意するのが作法なのだが、銀貨を使うまでに簡略化されたのは初めてだ。 その銀貨が曇りなく磨かれ、表面が濡れてなお、黒くくすんでいないことをよく確かめてから、指で摘み親指で弾いて返す。 少女はあわてて、自分のほうへ飛んできたそれを危なっかしく捕まえ。少々のうらみをこめ、ぶすくれ、おれを眇める。 やせぎすではあったが、人目を惹く顔をした少女だった。 とにかく眼がいい。古木のように堅牢な意志を覗かせたとび色の眼。それが、肩までのびた色の薄い黒髪とあわさり、歳の割りに大人びてみえる。 けれど表情は子供らしく不安定な動きをみせるので、恒常と変転という相反するものが同居して、見たものを捉えてなかなか離さない。 母は出かけています。 少女に、魔女はどこかと尋ねたら、返ってきた答えがそれだった。どこへ行ったのか、いつ帰って来るのか。そういった問いには一切答えず、目を伏してだんまりを決め込む。 にっちもさっちも行かなくなって、「それなら帰って来るまでここで待つ」と強引に押し通し、少女の手によってガラクタの山から掘り起こされた椅子にやれやれと腰掛け、今に至る。 "本物"の魔女とはどういうことか。村長は、「魔法を使う」と答えた。 それはどんな魔法か。尋ねたおれに村長は、「言葉ではとても説明しきらない」 そして魔女の家へ向かうよう勧めた。 勇者が魔女の家へ向かう。 それ自体はとても自然な物語だ。 魔女に対する村の支配はよそ者、普通は、勇者を介して行われる。 たいていの村で、魔女は村外の人物としか話すことが許されない。正確には、許されない、とは違うのだが。 村民が必ず、互いに対して魔女と会話することを禁じる暗黙の規律をつくるのだ。 会話したものは呪われると言い含められて育ち、実際に会話した、と誰かに知られたものは穢れたとして徹底的に迫害される。 にもかかわらず、人目につかず魔女の家へ訪れる手段だけは残す。 結果売春や中絶などの村の闇は、それらを引き受ける魔女と言う一点に封じ込められる。 言葉にするのもはばかられる秘密は、魔女と言う装置でろ過され、掻き出されたおぞましいものを横目に村のモラルは維持される。 おれは村長の言葉に従った。こうしてここへ来た。 だが、なぜここに来たのだろう。その理由は? ふと、思う。待ちくたびれ、退屈してきたせいで浮かび上がった、茫漠とした疑問。 暇つぶしにそれを頭のなかで追いかける。 おれがここに来た理由、それは村長に言われたからだ。 魔法やら、本物の魔女やらを知りたいと思ったから、その答えがあると言われた。 ……なぜそんなものを知りたいと思った? ようやく、おれはおれの中に名づけ難い義務感が走っていることに気が付いた。 どうにかしてその義務感の正体を暴こうと、頭を絞って、思考を手繰り、感覚の大元を見極めようとして。 「帰って下さい」 その言葉と共に、甘い香りのする小袋を顔に押し付けられ、思考は中断された。 袋をひっぺがしてみれば、どこかおびえたような顔で、少女が及び腰になっておれの前にいる。 「随分なご挨拶だな」 「帰って」 「お前の母とやらが来たら帰るさ」おれは、手に邪魔な小袋をなんとなく懐に納め、言った。「それまでは帰らない」 「……貴方は誰なんですか」 「おれか?おれは」どう答えるべきか思案する。この場合、勇者だと答えれば手っ取り早いのだが、そんな愚かな冗談を言う気にはどうしてもならなかった。 「……おれの名前は"フシュ"だ。 身分は、アイドル。 大衆の妄想するクソ下らない英雄譚につき合わされて迷惑してる根無し草だ」 「何を言ってるの?わかるように言って」 「ともかく、おれは村の混乱を正しに来た」仲間内で流行っている冗句を軽く流され落ち込みつつ、「いくらガキでも、最近村の様子がおかしいことくらいわかるだろう」 おどおどした態度から、生来のものであろう勝気なところを見せ始めていた少女は、とたんにしどろもどろになった。 「わたしは、あまり……。 この家にこもってて、村の事はあまりしらなくて、だから……」「おれは名乗ったぞ」 いきなり言葉をおっかぶされ、少女は目を丸くする。 「え?」 「おれは名乗った。次はお前。それが礼儀だ」 少女は、叱られたと思ったのか顔を赤くしてうつむき、悔しそうに声を絞り出した。 「ウル」 奇妙な沈黙、間、空白。 おれが言葉の続きを待っていると、困惑したような上目遣いで、少女はチラリとおれを見上げる。 それでようやく、『ウル』というのが彼女の名前なのだとわかった。 「……ねえ、貴方。混乱を正しに来たっていったよね、だったら――」 なにか言おうとしたウルは、乱暴に叩かれた扉の音に挫かれ、ビクリと震え、振り返った。 |
||
この小説は 面白い/ 面白くない *これは主にネット小説ランキングから来た人に向けた評価ボタンです。面白くない、についてはWEB拍手の機能を利用して集計しています。
|
||
 |
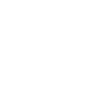 |

|
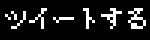
|
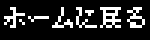 |