 |
 |
|
|
魔女。 魔女に対する一般的なイメージとは、どんなものだろう。 魔法を使う女。悪魔に仕える女。あるいは、魔性の女。 そんなところか。 けれど、それらは馬鹿馬鹿しいファンタジーでありオカルトだ。子供の夢だ。 大人になれば誰でも知っている。 魔女とはただの人間であり、悪意の受け皿であり、生と性をつかさどる不浄な存在だ。 ある集団を円滑に機能させるために、虐げられることを公認された必要悪だ。 ただの女でも、"魔"と頭につくだけでそれは虐げられるべき敵として機能する。 魔という言葉はおれたちと彼らとの決定的な差違を示す、好きなように踏みにじってよいという印だからだ。 それが例え不幸に埋もれた弱々しい女でも、領主の悪政に憤怒し義勇に駆られた男でも、魔と頭につけば単なる大衆の敵だ。 前者は魔女と呼ばれ、後者は魔王と呼ばれる。 なにかに間違いで彼らに協調した民は、魔物と呼ばれ、その運命を彼らと共にする。 それゆえ民は彼らを恐れ、阻害し、徹底的に孤立させる。 そして勇者と称される者は、ついに耐え切れなくなり怒り狂った彼らを、退魔と称して殺す。 それがこの世界で気の遠くなるほど永く続いてきた一つの構造。 異相矛盾の統合にして、歴史に研磨された迷宮。 だから、居てはいけないのだ、本物の魔女なるものは。 魔法も悪魔も、おれたちの想像力の作り出した幻想に過ぎない。 そんなものは妄想として、夢として、物語としておれたちの頭の内側に封印されねばならない。 霧でも立ち込めていれば少しはさまになっただろう、ぼろい小屋の前におれはいた。 例えば、沼のほとりに建ち、死んだ犬を道すがら串刺して晒し、しゃれこうべを軒先に引っ掛け、カラスがひっきりなしに降り立つ。 だが現実にそれな演出など存在せず、ぼろい小屋はただぼろい小屋として蒼穹のした、森のふちにあり。息も絶え絶えに今にも崩れ落ちそうな屋根をひん曲がった柱が懸命に支えている。 "本物の"魔女の家というにはあまりに貧相なつくり。 その面構えは苦痛にゆがみ、柱のひとつでも蹴っ飛ばせば崩れ落ちて、こんがらがった何もかもがスッキリ解決するように思われる。 もちろん、事はそんなに単純ではない。まったくもって、簡単でも明快でもすんなりとも行かない。 容易ならざるからおれはここにいて、勇者と呼ばれるものの使命を、背中をムズ痒くしながら全うしようとしている。 おれはよく手を揉んでから、細心の注意を払ってこぶしを振り上げ、腐り果てた扉を叩いた。 「ちーす」 返事はない。人の気配がないことに気づき、おれは遠慮なく踏み入ることを決めた。 錠前の本締はもはやその意味を成しておらず、少し力を加えただけで、湿った木屑をほじるようにして扉は開いた。 いいわけめいた言葉を小さくつぶやき、中に入れば、甘ったるい薬臭さに顔が歪む。 狭い。というのが最初の印象だった。 単純に狭いのではない。モノが床じゅうに広がり、積み上げられたせいだ。 立体的に迫ってくるそれらがおれの目を圧迫する。 はっきり言うのなら、だらしなく感じる。不潔な印象を受ける。 乾燥した動物の肝やら植物が所狭しと壁に引っ掛けられ、何か理由があるのか窓と言う窓は目打ちにされ、どういう用途に使うか見当もつかない道具や、分厚い本、書いては消してを繰り返したせいで薄くのびた羊皮紙がひたすらにうず高く積まれている。 溢れるモノのすき間によく眼をこらしてかろうじてわかる道、というよりは誰かが動いた跡を進み、比較的床の見えるかまど周りに近づけば、鍋から漂う鼻につくあまい香りと、作業台に載った、白い粉の詰められた袋に否が応でも気づかされる。 あらゆる意味でがさつなものを感じさせる空間のなか、その周囲だけは奇妙に整然としていた。 作業台に全く傾きがないこと、置かれた秤がよく調節されていることを確かめ、ふと眼を上げたさき、裏口と思われる半開きの扉のむこうに小さな畑があることを見とめる。 扉を押して覗くのは、強い日差しのなか咲き誇る、鮮やかな赤色の花。 大人が三人ばかり手を広げればまるまる囲えそうな、かわいらしい広さの畑に、その花は毒々しく茂っていた。 子狐か猫か小さな生きものが遊んでいるな、とぼんやり思いながら、風もないのに荒々しく揺れる花をしばらく眺めて、ようやく。 そこに埋もれて、少女が這いつくばり、汗水を垂らしながら土の様子を仔細に確かめているのだと気がついた。 |
||
この小説は 面白い/ 面白くない *これは主にネット小説ランキングから来た人に向けた評価ボタンです。面白くない、についてはWEB拍手の機能を利用して集計しています。
|
||
 |
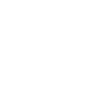 |

|
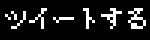
|
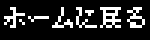 |