 |
 |
|
|
森から道なりに歩いて数分。 視界を埋めていた木々も失せ、むこうの丘まで見通せる平らな土地にひしめく畑とそれを貫く道とのあいだの草むら。 魔女の家へむかうとき通り過ぎた区画で一服する。 畑に向かって傾斜を奥にしたそこへ踏み入り、あぐらを掻く。 仕事に一区切りつけて、仲間と休んでいたのだろう、数名の老人が下方で駄弁っており、一度だけ見上げるようにしておれのほうへ目配せ。仲間との雑談を再開する。 おれは目を瞑り、しばらくして、自然と瞑想に入る。 どうにも事態が複雑で、嘘と隠し事が充満しているように思える。 言葉としておれの前に現れた情報が、一つとして確かでない。 この仕事で食ってる身として言えば、そういった入り組みはままあること。 WHOの武官という身分すらどこか空々しいものにしか感じないおれが、仕事の流儀について語るなど滑稽そのものなのだが、それでも入り組んだものをそのままにして、いい加減に処理することは気に食わなかった。 立ちはだかる無形の情報と、言語で対決するのははなはだ心もとない。 言語で組み立てる論理に頼る事が出来ないのなら、感覚に身をゆだねるしかない。 古くに霊感や啓示と呼ばれるもの。 いかにも魔術的で胡散臭いが、その実態は、この身に入力された言葉ならざる情報を解きほぐし、行き当たりばったりにほぐされたものを脳が関連付け、筋の通った連なりを言葉によらず見出すこと。 学ぶことも教えることもできない、秘された場所にある知恵。 おれは思考とも呼べないそれが機能することに賭けて、ぼんやりとした時を過ごす。 足元から老人たちの会話が聞こえる。 「――さんとこのは」 「最近うちに帰りもしない。悪い仲間と遊んでばっかり」 「あのなんとかっていう」「ヴェスパー」 「あいつが来てから真面目じゃなくなって」 「村長はなにをやってる」 「わしらが推挙してやった恩も忘れよってからに」 「忌々しい――」 「――大体からして、あの若造、学校なんぞ作ろうとしたときからおかしかった!」 突然の大声におれは薄目になり、気付かれないよう視線だけを下げて、老人たちのほうを見た。 声を張り上げた老婆の横で、禿げたジジイがパイプをふかしながら、にたりと笑う。 「あのときは必死になったなぁ」 「ガキを取られちゃワシらがやっていけん。学なんぞ身に着けると村から離れる。学なんぞただの毒じゃ」 「村長の玄関先がクソまみれになったのは凄かった」 「犬の死骸が屋根に引っ掛けてあった」 「窓と言う窓を叩き割ってやったぞ」 「こらこら、あれは魔女の仕業。そういうことになった。ワシらには関係ない。 ――しかしあの若造が中止を発表したときは、スカッとしたのう、ええ?」 どっ、と汚らしい笑い声が沸く。 おれはそろそろ、傾斜のしたにあるものが肥溜めだということに気付きはじめる。 悪意と嫉妬、愚か者の無知と、弱者の驕りの、肥溜め。 「しかし実際問題どうなるか」 「あのヴェスパーとかいうよそ者は人殺しじゃ、わしらじゃどうにも」 「どうせあのよそ者を呼び寄せたのも魔女なんじゃ、忌々しい」 「まあ、なんにせよ、勇者さまがどうにかしてくれるさ」 おれはそのことばを聞いた瞬間に立ち上がって、足早にその場を去った。 気分の悪いものを耳に入れてしまった。 脳が腐るほどにおぞましい弱さ。 すぐには処理し難い、胸につっかえたむかつきを持て余しながら、足を動かすことでそいつを振り落とせるような気持ちで、いつしかおれは駆けていた。 「誰か殺してきたのか」 書斎に入ってきたおれの様子を見るなり、村長は目を険しくしてそう言った。 首筋に手を当ててみれば、べとりとした汗と荒れる動悸に気付かされる。 思わず舌打ち。あのクソカスどもの言動でみっともない姿を見せる羽目になった、そのことに苛立つ。 「おれだって殺す相手くらい選ぶさ」 「殺したくなるくらいの奴がいたか」 「大抵の奴がそれだ」 「下がりなさい」 つま先で空いた椅子を引っ掛け、引き寄せ、靴を蹴り脱いで、その上にあぐらを掻く。そのあいだに村長は、半開きの扉のむこう、玄関からおれを追いかけてきて、今は鬼の形相をして廊下からおれを睨みつける村長夫人に語りかけた。 「また絨毯を汚されました。泥除けも使えない野蛮な人は、もうこの家に上がらせないと言っておいて!」 「言わない。君がどう思おうが彼はこの村の英雄だ」 「随分汚らしい英雄がいたものですわ!」 「彼はほかの誰にも出来ないことをやってのける。私でも、君でも無理だ。 この村の人々が束になってもできっこないことを平然とやってのける。だから自然と敬意を集める」 「ええ、ええわかっていますとも――ひとの家を汚さないなんて、当然のことはおできにならないのに!」 勢い良く閉じた扉の音に身をすくませて、一言。 「耳に痛い」 「お前が無神経すぎるんだよ」 上等な椅子に背を預けて、執務机に向かったまま村長がぼやく。 「いい奥さんだな、領主の娘か」 「五女だ。子どもが出来ないことに気を立ててる。 悪いがアレはそっとしてあげてくれないか」 「これからは。ここに来るとき注意する」 言い回しを不審を持ったのか、首を傾げた村長に、駆けながら考えていたことを言っておく。 「この家を離れる。悪かったな、色々荒らしたみたいで」 「待て、そこまで気を使うことは……」 違う、と俺は勘違いをした村長に説明。 「やらなきゃならんことができた。これからは魔女の家に泊まる、と言ってるんだ」 「何かあったか」 村長は机から身を乗り出した。意外なほど感情的な反応。おれはその奇妙さをあえて指摘しないまま、こっそりと村長の様子に注意する。 「魔女のガキが客にクスリを渡してた。おれも渡されたからまず間違いねぇ、来る人来る人に渡してるぞあれは。 肝心の魔女はいなかった。 何かが狂ってる。かみ合っていない。なにがなんでも魔女と話す必要がある。そして――」 「殺すか」 「当然だ。二代目がいるなら躊躇する意味もねぇ。管理不届き故ってやつだよ、おかしいか?」 いいや、と村長は否定する。だがおれは気付いている。理屈で正しいと思っていても、この男はそれを正しいことと思っていない。眦【まなじり】にかけられた力が、かすかに噛まれた唇が、それを示している。 だがおれはそれを指摘しない。おれは無神経だが、友人が隠したがっているものを取り立てて暴くほど腐ってはいない。ましてそれが無意識によるものなら、なおさら。 「怠け者のお前が、こんなつまらないことで、どうしてそこまでする」 「たまに本気で失礼だな!」 「真面目に言ってるんだ」 なおさら失礼じゃねぇか、と怒りながら、魔女の家で待たされていたときからずっと考えていたにもかかわらず、俺自身それに対する答えを用意できていないことに気付く。 「習慣、仕事、役割――さぁな、わからん」 「……ほんとうに気付いていないのか?」 「自分はわかってるって口ぶりだな」 あきれたように村長は首をゆっくりと振り、 「お前の偽悪っぷりにはいつも驚かされるよ。 自分には善意がひとかけらもないと思っているだろ」 「見返りを期待するような浅ましいモノなら持ち合わせちゃいないが、 誰かを救おうって気持ちならある。あいにく発揮する機会なんてそうそうない」 世の中、救うに値しないクソな奴らばかりだ。忘れていた胸のむかつきを思い出す。それを吐き出すようにして、おれは言った。 「ただおれは、おれがあるがままにしているだけだ」 それを聞いて、そうか、とどこか寂しそうに村長は笑い、「今日の宵の鐘【ヴェスパー】」と言った。 「なんだって?」 「葬儀の時間だ、アーネストのな。知りたかっただろ」 「だれがあんな、ただ見かけただけの酔いどれ」 「出発は明日にしろ。徹宵【てっしょう】の祈りを捧げるよう、修道士には言っておいた。 あの男はこの村のほとんどの家を建てた。この家だってそうだ。 誰よりも村を愛した、みんなに愛された男だった」 しらねぇよ、と言って。居心地が悪くなって、おれは書斎からそそくさと出た。 扉を開けると、少し離れたところに村長夫人がいて、小躍りして喜んでいた。 おれに気がつくとさすがに踊りはやめたが、浮かんだ笑みを隠すそぶりもなかった。 「ええと、しばらく迷惑掛けまして――」 「ええ、ほんとにそう」 「これから用事があって出かけますが、明日荷物をまとめて出ますんで」 「あら、いってくれれば荷物を運ばせますのに。なんなら今すぐにでも」 本当に、こちとら怒りも浮かびようがないほど、すがすがしく婦人は笑ってみせた。 |
||
この小説は 面白い/ 面白くない *これは主にネット小説ランキングから来た人に向けた評価ボタンです。面白くない、についてはWEB拍手の機能を利用して集計しています。
|
||
 |
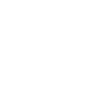 |

|
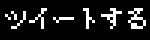
|
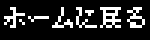 |